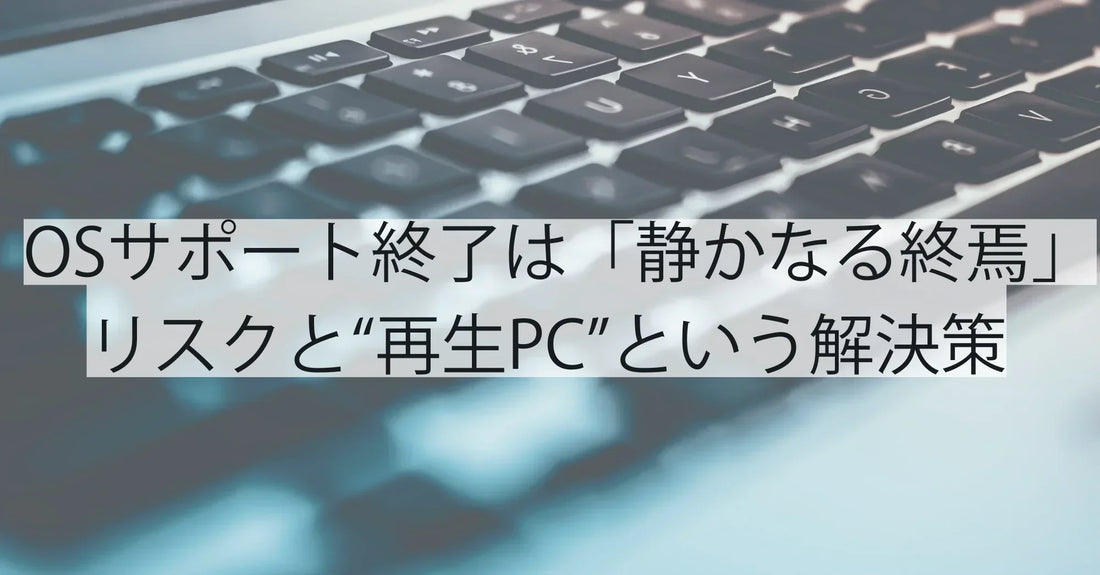
OSサポート終了は「静かなる終焉」―見落とされがちなリスクと“再生PC”という解決策
Share
1. OSの「終わり」は静かに訪れる
OS(オペレーティングシステム)のサポート終了は、日常的なアラートも、派手なニュースもありません。ただし、それは「目立たない」だけであって、重大なセキュリティと運用リスクを同時に内包する“静かなる終焉”です。
アップデートを受け取れないOSは、時代の進化から切り離された「孤島」のような存在。見た目は通常通り動いているかもしれませんが、その内部では、世界から取り残されたインフラが崩壊へと向かい始めているのです。
2. OSサポート終了がもたらす5つの重大リスク
① セキュリティの崩壊
サポート終了後は、マイクロソフトなどの提供元からセキュリティパッチが一切配布されなくなります。ゼロデイ攻撃、ランサムウェア、フィッシング、スパイウェア──こうした脅威は日々進化しており、OSが停止した時点で、防衛力は“時間に取り残される”ことになります。特に、業務PCでのクレジット情報、顧客データ、ログイン情報は狙われやすく、個人被害だけでなく法人の信用失墜につながる深刻なリスクを抱えます。
② ソフトウェアとの互換性消滅
業務アプリ、メールクライアント、ブラウザなどの主要アプリケーションは、サポート対象OSでの動作が前提です。OSのバージョンが古くなることで、ソフトウェアやクラウドサービスが非対応となり、業務に支障をきたす可能性があります。
③ 周囲への被害(サプライチェーン攻撃)
脆弱なOSは、自社だけでなく、取引先や委託先にまで被害を及ぼす媒介となります。近年では「サプライチェーン攻撃」が増加しており、攻撃者は大企業ではなく「セキュリティ対策の甘い下請け」を経由して侵入する手口を多用しています。
④ コンプライアンス違反の懸念
個人情報保護法や情報セキュリティガイドラインでは、「必要な情報セキュリティ措置を講じること」が義務付けられています。古いOSのまま運用を継続することは、リスクを認識しながら放置している=未対応と見なされるリスクがあり、監査時や事故発生時に問責される可能性も否定できません。
⑤ 意思決定の遅延・判断ミス
多くの企業がOS更新を「コスト」と捉えがちですが、実際には放置による被害額の方が大きいのが現実です。技術者不足や運用リソースの逼迫により、「分かっていても対応できない」という“見送り判断”が積み重なり、結果として組織のレジリエンス(復元力)を奪っていきます。
3. なぜ「再生PC」が有効なのか?──持続可能性とコストバランス
Windows 10のサポート終了(2025年)を控え、再生PC(リユースPC)が注目されています。R∞PCは次世代の再生PCとして高品質・安心サポートを兼ね備えています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 保証 | 無期限保証(自然故障も過失も対象) |
| サポート | 無期限電話サポート(全国対応) |
| OS | Windows 11 正規MARライセンス搭載 |
| 品質管理 | 自社再生工場による徹底整備&クリーニング |
| 対象者 | 学生、社会人、シニアまで幅広く対応 |
4. OS移行と向き合う組織的アプローチ
- リスクベース思考でのIT資産見直し:「使えるか」ではなく「安全か」で判断。サポート終了予定のOS台数を棚卸し、導入機器ごとの依存サービスも同時に洗い出します。
- 対応の優先順位を明確に:外部ネットワーク接続PCは最優先で更新。内部業務専用機は延命施策(仮想パッチ等)を、汎用機・予備機はR∞PCなど再生品での置き換えを検討します。
- 情報発信と社内教育:OSサポートの重要性を全社レベルで共有し、社員の自己判断による使用継続を防止。対策完了状況を見える化(進捗ボードの導入など)します。
5. IT資産に「新陳代謝」を
サポート終了OSを放置するのではなく、今こそ「IT環境の健康診断」を。
- 安全性
- 維持コスト
- サポート体制
これらを基準に、「使える」ではなく「守れるIT環境」への移行を検討しましょう。
R∞PCダイレクトでチェック!

